- お支払い方法について
- クレジットカード決済のみ対応しています。





- 送料について
- 合計購入金額21,600円以上で送料無料!
詳細な送料についてはこちらをご覧ください。
- 配送方法について
- 配送方法についての詳細はこちらをご覧ください。
- 返品について
- 商品がお手元に届きましたら、すぐに内容のご確認をお願いいたします。
返品・交換についての詳細はこちらをご覧ください。

ろくろ舎|BASE01シリーズ 飯椀
再入荷待ち
6,600円~
色とサイズを選択
※再入荷した際に、メールでお知らせします。
※再入荷・ご購入を約束するものではありません。
※再入荷・ご購入を約束するものではありません。
※ご利用条件はクーポン詳細をご確認ください
- 購入金額が税込21,600円以上で送料無料
飯椀にも漆器を。

高台を高く、大きく存在感のある形に仕上げたろくろ舎オリジナル「BASE 01シリーズ」の飯椀です。しっかりとした高台はデザインとしても秀逸ながら、手に取りやすくて持ちやすく、安定感も生まれます。美しい漆器の飯椀は、本当にごはんがおいしそうに見えます。白米、玄米、雑穀米、炊き込みご飯を盛り付けても、より一層引き立ちます。
BASE 01シリーズ

漆器のベースを作り出す「木地師」が提案する、本来であれば隠れてしまう木地の美しさや下地の素材感を活かしたプロダクトラインのBASE。中でもBASE 01シリーズは器を支える土台である高台部を力強く強調した器のシリーズです。
ろくろ舎のコンセプトが表れた、美しいプロダクト。

径:約11.4cm 高さ:約6.5cm 使いやすいサイズと深さ。
漆器の飯椀をお使いの方はあまり多くないかもしれません。ですが、漆器は手に持った際に熱くなく、よそったものが冷めにくいのが特長。飯碗や汁椀に最適です。この飯椀は適度に深く作られているので、ごはんを入れるだけでなく、ちょっとした汁物や、煮物の小鉢など、様々な使い方をしていただけます。

しっとりとなめらかで美しい内側。

重ねて収納しておけます。ぴったり重なる美しさも、ろくろ舎のプロダクトの魅力のひとつ。

箱に入れてお届けします。贈りものにも。
4種類からお選びください
木目の表情の美しさを味わえる「拭き漆」

黒拭き漆、生拭き漆
縞模様が美しい「乱筋」

乱筋黒拭き漆、乱筋生拭き漆

乱筋は、側面に筋が入り、その筋に染み込んだ漆が縞模様になる。
お揃いで使いたい。

左:飯椀 右:汁椀
深さと口の広さが異なる飯椀と汁椀で食卓を揃えるのもおすすめです。

6,600円~
再入荷待ち
ろくろ舎

越前漆器の産地福井県鯖江市で、丸物木地師として伝統的な技術を継承しながら”価値の再定義”をコンセプトに、木材を中心に素材、製法にこだわることなくプロダクトを製作している「ろくろ舎」。
漆器作りには、木地師、下地師、上塗り師、蒔絵、沈金師などそれぞれ専門の職人がいます。ベースとなる木地作りを担当するのが木地師で、中でも椀のようにろくろで丸く挽く木地師を丸物木地師と呼びます。ろくろ舎は、この伝統的な丸物木地師の技術を継承しながら、椀をはじめ、器やインテリア、アクセサリーなど、幅広いプロダクトを制作しています。
また”持続可能”をテーマに、福井の間伐材を使用した商品開発をプロデュースする、自分だけの椀をオーダーできるオンリー椀というイベントを開催するなど、漆器や職人、その産地である鯖江・河和田地区に循環を生むため、作り手の領域に留まらず様々な活動を行なっています。
漆器作りには、木地師、下地師、上塗り師、蒔絵、沈金師などそれぞれ専門の職人がいます。ベースとなる木地作りを担当するのが木地師で、中でも椀のようにろくろで丸く挽く木地師を丸物木地師と呼びます。ろくろ舎は、この伝統的な丸物木地師の技術を継承しながら、椀をはじめ、器やインテリア、アクセサリーなど、幅広いプロダクトを制作しています。
また”持続可能”をテーマに、福井の間伐材を使用した商品開発をプロデュースする、自分だけの椀をオーダーできるオンリー椀というイベントを開催するなど、漆器や職人、その産地である鯖江・河和田地区に循環を生むため、作り手の領域に留まらず様々な活動を行なっています。
使用上の注意点
木製品のため、電子レンジ、食洗機、蒸し器などには使用しないでください。
また色が焼けてしまうことがありますので直射日光はお避けください。
また色が焼けてしまうことがありますので直射日光はお避けください。
返品・交換についての注意事項
手作り品の為、ひとつひとつが微妙に違います。お客様都合での返品、交換につきましては配送料をお客様のご負担でお願いいたします。未使用品であっても、大きさ、デザインもしくは色のイメージ違いによる返品・交換はお客様都合になります。ご利用のブラウザ、モニターの性能、設定により商品の色、素材感等につきましては、 現物と若干の違いが出る場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
わざわざのアイテムを人気順にチェック!

「よき生活者になる」を合言葉にわざわざでは独自の選定基準を定めて、衣食住にかかわるこだわりのアイテムを多数取り扱っております。キナリノモールで人気のあるアイテム順に是非チェックしてみてください!

茶碗・お椀の人気ランキング
このストアの新着ストアレター
ストア紹介
パンと日用品の店〈わざわざ〉は長野県東御市御牧原の山の上にポツンと佇む小さなお店。“よき生活者になる”を合言葉に、薪窯で焼いたパンと、食と生活それぞれの面から、独自の選定基準を定めて自分たちが心からよいと...もっと見る




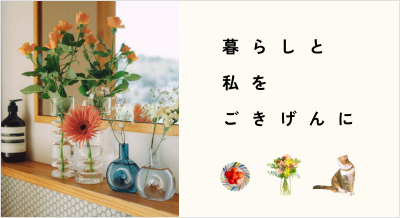


























































左から 黒拭き漆、生拭き漆、乱筋黒拭き漆、乱筋生拭き漆